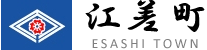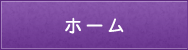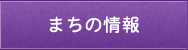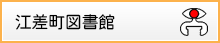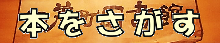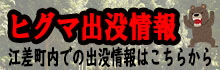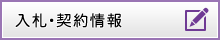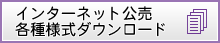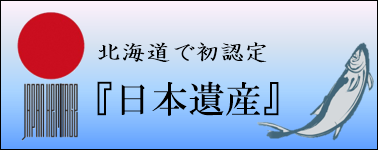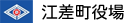五勝手の鮫踊り

五勝手鹿子舞が、椴川山、古櫃山、豊部内川南面で伐採にあたった杣夫たちによって山神神社(現檜山神社)を中心とする山岳信仰と結合して発生したものであるのに対し、五勝手地方に盆踊りの形態として伝承されてきた鮫踊りは、鰊の大漁と海上安全を祈願する素朴な庶民の願いを表現したものとして受け継がれてきました。
鰊漁華やかなりし頃、鮫は甚だ厄介な存在でありました。網を食い破り、網に入った鰊を食い荒らす。鰊の漁道に出現してはその進路を変えてしまう。鮫が網に入ると、これを引き上げるには重くて手に負えぬという文字通りの海のギャング、暴れ者でありました。
そこで漁師たちは手に手に棒を持って網の中の鮫を叩き殺すという、原始的な対策をとらざるを得えませんでした。その数おびただしく、撲殺された鮫の血で海面が真赤に染まったといいます。
鮫踊りはこのようにして撲殺された鮫の霊をなぐさめる意味で、網の中でのたうち回るさまを踊りにしたものだといわれています。
また、これとは別に、鮫が沖を回遊すると、それに追われて鰊が陸近くまで群来るので、鮫こそ漁の神様、だから感謝をこめた踊りだとする説もあります。
明治11年8月4日付、函館新聞に記す。江差町招魂祭は例年7月20日、祭日なりしが祈り悪しく雨天続きにて、ようやく去る30日行われた。余興に移り、サメ踊りが行われた。このサメ踊りは、この海岸にて橦木サメというものありて、ニシン漁のとき大いに害をなす魚なりとて漁民どもはそのサメを神にあがめて祭りをなす。
盆踊りといっても、鮫の姿を踊りに表現したものだから、その動作は激しく、体を前後左右にくね曲げるので、年配者には耐えがたいほどの踊りであり、体の柔軟性を要求されるところから女性に適した踊りである。
うら盆中、柏森神社や寺の境内で、時には前浜で、夕方から男女相興じて唄に合わせて踊り明かす。
時には部落をあげて張子の大きな鮫を先頭に、江差の問屋街にくりこみ、デモリながら祝儀をせしめ、海産物の値上げ要求行動に出ることもあったという。だから、サメは役人や親方を模したものと、一揆の影を感じとる人もいるといいました。
【お問い合わせ先】
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 追分観光課 観光係
TEL:0139-52-6716
FAX:0139-52-5666
社会教育課 地域文化係
TEL:0139-52-1047
FAX:0139-52-0234
|
江差三下り |
江差の郷土芸能 |
土場鹿子舞 |
まちの情報open
概要open

面積 : 109.53km2 (前月比) 人口 : 6,399人
(-6人)
男 : 3,089人
(-0人)
女 : 3,310人
(-6人) 世帯数 : 3,917世帯
(-3世帯)
(令和7年12月末現在)
-
サブナビゲーションopen
-