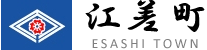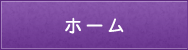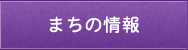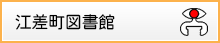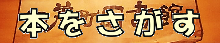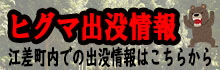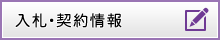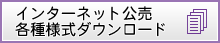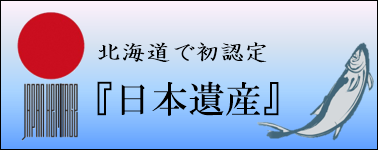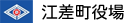令和7年度教育行政執行方針
1 はじめに
令和7年第1回江差町議会定例会の開会にあたり、江差町教育委員会の所管する教育行政の執行に関する主要な方針を申し上げます。
社会の大きな変革期にあって、従来の知識や経験だけでは「解」を見出すことが難しい時代となっているなか、本町の持続可能な発展のためには、人づくり、地域づくりの基盤である教育の役割は極めて重要であります。
このため、これからを生きる子どもたちが、様々な困難を乗り越え、未来を切り拓いていくために必要な資質・能力を育むため、「地域に学び、人を育てる」をコンセプトに、これまで以上に学校・家庭・地域・行政との連携を深めていかなければなりません。
また、社会教育活動を通じた人づくり・つながりづくりは、地域づくりに直結するものであり、町民一人ひとりが、生きがいと喜びを持ち、生涯にわたって学び続けることができる場の整備が必要です。
このような中、令和7年度は、令和8年度から始まる江差町教育大綱並びに江差町教育推進計画の改定期にあることから、町長部局と連携を図りながら、教育を取り巻く環境や社会情勢の変化を的確に捉え、学びと育ちに関する実効性のある計画の策定に取り組みます。
江差町教育委員会は、全ての教育活動における「幸福」の持続可能性を追求し、町民の皆さまが生涯にわたって活躍できる教育環境の実現に向け、教育行政を推進してまいります。
以下、令和7年度の学校教育、社会教育の各分野における考え方を申し上げます。
2 学校教育の推進
「ふるさと江差に心の向く教育の推進」を掲げ、令和3年度から現在まで江差町教育推進計画をもとに特色ある教育活動を展開しながら子どもたちの育成に努めてきました。
本年度は、江差町教育大綱及び江差町教育推進計画の改定期であり、これまでの取り組みを振り返りながら、学びの現在地を的確に捉えるとともに、全ての学校教育活動に「探究」を位置づけ、次期の江差町の教育のあるべき姿の土台づくりを進めます。
はじめに、学力の向上についてですが、令和の日本型学校教育の柱に学校のICT化が掲げられ、子どもたちの学習形態も大きく変化しています。
本年度は、現在使用しているICT端末の更新期にあたることから、国の補助を活用し、町内の全小中学校へ新たなICT端末の整備を実施します。
一方、子どもたち自らが直接、見たり、聞いたり、触れたりといった五感を通じた感性という力を育むことも重要です。
このため、デジタルとアナログの融合を意識しながら、子どもたちそれぞれの学習意欲を向上させるとともに、家庭学習の定着化を図り全体の学力向上に取り組みます。
また、これらを実現する上で、教職員の資質や能力の向上が不可欠であることから、実践的指導力を高める校内研修を推進します。
さらに、学びのカタチづくり推進モデル事業を活用し、校長裁量のもと特色ある学校づくりを進めます。
特別支援教育については、子どもたちの持つ特性を理解し、充実した学校生活を送ることができるよう引き続き学習指導員や特別支援教育支援員を配置します。
また、本年度から新たに町内の小中学校に通級指導教室を開設し、個々の教育ニーズに応じたよりきめ細かな指導を行います。
さらに、幼保小中が互いに連携し「より良くつなぎ、15の姿に責任を持つ」を合言葉に昨年度から始まった「かけはしプロジェクト」を前進させ、様々な課題の解決に努めます。
いじめや不登校については、日頃から学校現場において、子どもたちの小さな変化を見逃すことなく対応にあたっておりますが、本年度は、従来のいじめアンケートに加え、子ども発達理解支援ツール「ハイパーQU」を活用するなど一歩踏み込んだ実態の把握に努め、適切な対応を図ります。
本年度から学校給食については、江差町が主体性を持って運営することになることから、新たな地場産品を活用したメニューの充実を図るなど、これまで以上に安全でおいしい学校給食の提供に努めます。
また、引き続き、学校給食費無償化事業を実施し、保護者の負担の軽減に努めるとともに、本年の8月に江差町で開催される「第66回北海道学校給食研究大会江差大会」の準備・運営に万全を期します。
子どもたちの教育環境や、教職員の働く環境の整備は、教育効果を上げるための一番の近道であり、この間、小学校への複合遊具の設置、町内全校へのエアコンの整備などを行ってきました。
本年度は、南が丘小学校体育館照明のLED改修工事を実施するとともに、今後も施設・設備の計画的な整備や、教材・教具の充実などに努めながら豊かな学びが実現できるよう意を尽くします。
3 社会教育の推進
社会教育は、『生涯学習』として、知識の習得や能力の向上はもとより、生きがいや充実した生活を送るため、子どもから大人まで幅広い世代が生涯にわたり学習する機会を提供していくことが必要です。
「江差町の子どもたちは、町民の手で育む」という想いのもと、各学校に設置されたコミュニティスクールの活動を通じて、学校・家庭・地域が一体となった「地域とともにある学校づくり」を推進します。
部活動の地域移行については、江差町中学校部活動地域移行検討協議会を中心に、地域での受入先や指導者の確保など、関係団体や近隣町との協議を行い、可能な種目の地域への移行を進めます。
地域の特色を活かした多様な生涯学習活動の推進については、「みんなで育てるえさしっ子運動」による青少年健全育成活動、PTAと連携した家庭教育の推進など、子どもの健やかな成長を支える取り組みをはじめ、シニアカレッジ江差学園の活動など、各世代が楽しく学習・交流ができる機会の充実に努めます。
また、子どもたちや親子が安心して遊びや交流ができる場として、冬期間に文化会館で開設している「わくわく子ども広場」を引き続き実施するとともに、本年の11月に江差町で開催される「第58回北海道ユネスコ大会」の運営を支援していきます。
「読書はこころの栄養素」です。
図書館活動については、幼児期から高齢者まで多くの町民が本に親しみ、豊かな心を育むため、企画展の実施やフリースペースの開放など、更なる利用促進に向けた取り組みを積極的に展開するほか、学校図書館の活動を支援していきます。
誰もが健康で元気に心豊かな生活を送るためには、スポーツや芸術・文化活動の機会の充実が必要です。
生涯スポーツの推進については、水泳やスキー授業における学校との連携協力をはじめ、パークゴルフやスポーツ少年団等、各団体の活動支援を行い地域のスポーツ環境の充実に努めます。
また、連携協定を締結している北海道コンサドーレによるスポーツ教室やプロ野球OB会による少年野球教室を実施します。
文化振興については、江差町文化協会と連携し、各団体の活動の支援を行うほか、文化会館の利用促進に向けた取り組みを進めるとともに、屋上塔屋の防水改修工事を実施するなど施設の適切な維持管理に努めます。
また、本年度は、小学生を対象とした劇団四季によるミュージカル公演を開催し、子どもたちの芸術鑑賞に親しむ機会を提供します。
本町には数多くの文化遺産があり、これらの貴重な資源を後世に保存・伝承していかなければなりません。
文化財の保存・活用については、江差町歴史文化基本構想の具現化に向け、「エエ町、江差 宝箱会議」の取り組みを通じて、文化遺産をまちづくりに活かすための仕組みを検討するとともに、旧中村家住宅の鉄骨階段の改修を実施するなど文化財施設の適切な維持管理に努めます。
博物館活動については、郷土資料館の所蔵資料の整理を進め、北海道デジタルミュージアムでの公開や、企画展の開催による博物館機能の充実を図るほか、地域の歴史文化の素材を学校授業で活かす「ふるさと江差発見学習」に引き続き取り組みます。
開陽丸は、国内でも数少ない貴重な水中遺跡であり、100年先の未来へしっかりと本物を遺していくことが、私どもに課せられた使命であるとの認識のもと、引き続き、国の補助を活用し、海底で保存している大型船体の現状確認調査を進めるほか、既に引き揚げられている遺物についても、資料の整理や保存環境について調査を進めていきます。
4 むすびに
「世界では火薬は戦いのために使われている。僕の国では、火薬は花火に使われ大空に咲きます。」
この詩は、江差ユネスコ協会の皆さんが主催する少年野球大会に参加した子どもの作文の一端ですが、この詩から、子どもの感性の豊かさはもとより、平和であることの尊さや命の大切さが伝わってきます。
江差町教育委員会は、このように誰もが有している資質や能力といった可能性を引き出し高めていくため、引き続き、子どもをど真ん中に据え、全ての世代における価値ある個々の存在を認めながら、SDGsの理念である「誰ひとり取り残さない持続可能な地域社会の実現」を教育分野で実践します。
こうした考えのもと、あらゆる世代が健やかで、ふるさと江差に誇りと愛着を持ち、明るい家族の団欒と、生きがいや幸福を実感できる地域づくりに向け、全力で教育行政を推進してまいります。
町民の皆さま、町議会議員の皆さまのご支援とご協力を心からお願い申し上げます。
|
教育行政執行方針 |
令和6年度教育行政執行方針 |
くらしの情報open
概要open

面積 : 109.53km2 (前月比) 人口 : 6,389人
(-10人)
男 : 3,082人
(-7人)
女 : 3,307人
(-3人) 世帯数 : 3,910世帯
(-7世帯)
(令和8年1月末現在)
-
サブナビゲーションopen
-